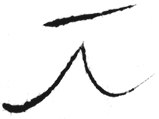未来を写した子どもたち
未来を写した子どもたち
アメリカ/2004年/監督:ロス・カウフマン、ザナ・ブリスキ
ドキュメンタリー映画。インド・コルカタの売春婦の生活を取材・撮影しようと、その地に滞在していた女性カメラマンが、その売春窟で暮らす子どもたちと触れあううちに、その子らに興味を持ち、写真を教えるようになる。
売春窟で暮らす人々というのは、特殊な環境であるため一般社会から隔離されているといったような状態だ。そこで生まれ育った子どもたちは、社会的な偏見や親の考え方、経済的な理由などいろいろな弊害が生じて簡単には教育を受けられない。
でも子どもたちの中には、教育を受けたいと思っている子どもはいる。教育を受けたいと思っても、どうしたら教育を受けることができるのか、その術を知らない、親も子も。それが教育を受けないということの悪循環ではないか。
子どもはそのまま大きくなれば、近い将来は売春婦、女たちの世話をする晩春窟の男になるのみ。それが親が子どもに教えられるただ一つの職業だからか。
でも本当はそうではない。なれる職業が一つしかないなんて嘘だ。この作品の監督である女性カメラマンのザナ氏は、この子どもたちに写真を教えながら、この売春窟から抜け出せる可能性があるということを教えた。子どもたちの撮った作品の写真展を開き学費を集め、学校に入学するための書類を集め、複雑な手続きに奔走する。
そんな悲劇のような環境に生まれ育った子どもたちであるが、普通に明るいし、屈託ない。でもやっぱり普通じゃない。
10歳~14歳、インタビューに答える口調はめちゃめちゃしっかりしている。自分が今、或いは今後しなければならないことがちゃんとわかっている。写真について学ぶ吸収さ加減が尋常でない。
もともと画を描くのが好きだったりして芸術的センスが最も光っていたアヴィジットくんなんぞは、目つきがもうギラギラしているし、11歳だから日本でいうと小5か、小5でそんな撮り方するか?!!というようなアングルで撮ったりする。子どもたちの写真はイキイキし過ぎて、ジェラシーだ・・・
ザナ氏の苦労の甲斐あって、子どもたちへ学校の門は開かれるのだが、ここで彼らは究極の選択を迫られる。寄宿学校のため親元から離れなければならない。10年程の課程が終了するまで家に帰ることが許されないとか・・・人手がなくなるからと親から反対されている子もいる。一歩踏み出すには余程の覚悟がいる状況。こんな10歳やそこらの子が、そんなこと自分で決めなければならないなんてさ。
けれども、こんな極限状態に身を置いているからこそ、しっかりと意志を持って、目をギラつかせていなければ生き残って行けないのかもしれないし、そんなギラギラした子どもが育つのかもしれない。ぬるい日本とは明らかに違う。
映画の終わりに、子どもたちのその後(2年後)の動向がテロップで表示される。やっぱり現実はそう甘くないか・・・とがっくし来て帰りの車の中でいろいろ考えた。義務教育はいいことか、よくないか。ありがたいか、ありがたくないか。
家に帰ってから映画のパンフを見た。日本で公開されてパンフができた頃の、更に4年後の子どもたちの動向が書かれていた。やっぱりザナ氏の行ったことは響いていなくはなかった。あの子らや、その他のあの地の子どもたちや或いは世界の子どもたちの未来にも繋がっているのではないか。
映画館のお土産、パンフの文化は素敵だった。